<目次>
1)今度はアフリカへ
2)「大使館」という職場
3)わたしの担当業務
4)中央アフリカという国家
5)ある日の出来事
6)バンギでの日々の生活
7)中央アフリカが教えてくれたこと
8)〔番外編〕『夢枕〔バンギ編〕』
※出典:湯本浩之「知ったことを伝えるために」有田典代(編著)『国際交流・国際協力の実践者たち』国際交流・協力活動入門講座Ⅲ、明石書店、2006年、177-179頁を参考に大幅に加筆。
1)今度はアフリカへ

教員採用試験に不合格となり、10月から大学に復学してからは、1年の時からずっと単位を落としてきたフランス語の授業を取り直して、卒業論文を慌てて書き終えました。そうしている間にも、再び海外に出かけることはできないだろうか、できれば海外で収入が得られるような仕事がないだろうかと考えるようになっていました。というのも、「世界一自由で豊かな国」だと信じて疑わなかったアメリカに光と影があったように、自分にはもっと知らなければいけないことがあるように感じていたのです。
そういうわけでアメリカのような“先進国”ではなく、“途上国”、それもアフリカのどこかの国に行ってみたいという思いを巡らしていました。当時、アフリカ各地が深刻な干魃に見舞われていました。とくにエチオピアでは大飢饉*1が発生し、100万人が餓死するなど、国際問題となっており、日本でも報道が続いていたことに影響されていたのかも知れません。
しかし、海外に職を求めると言っても、現在のようにスマホを使って簡単に海外の情報が手に入る時代ではありませんでした。そこであちこち書店をめぐっては本や雑誌を立ち読みして情報を集めました。当時、青年海外協力隊の存在は知っていました。ところが、いざ応募しようとしてみても、文系で新卒の私が応募できる職種はないと諦めました。
そんなある日、本屋で手に取った何かの雑誌の中に「在外公館派遣員*2」という聞き慣れない職種の広告を見つけました。それによると、①仕事の内容は「便宜供与*3」であること。②任期は2年間であること。③応募資格は20歳(高卒)以上で、④自動車の普通免許を所持していること。そして、⑤派遣国の言語を実用できることでした。「便宜供与」という仕事の中身は分かりませんでしたが、自動車免許さえあれば、ほかに資格は必要ない、アフリカに行けるのではないかと期待して、応募しました。
その時に募集されていた派遣国はアフリカの中では、セネガルと中央アフリカの2ヵ国をしかありませんでした。いずれの国も未知な国でしたが、調べてみるとどちらもフランスの植民地だった国で、公用語はフランス語でした。面接の時に「フランス語はできますか?」と質問されましたが、「第二外国語でした」と答えるのが精一杯でした。試験の結果、幸いにも採用されることとなり、派遣国は中央アフリカ共和国と決まりました。事前に外務省内の会議室で1週間ほどの事前研修があり、外務省や大使館について、任国事情や健康管理について、そしてプロトコール(外交儀礼)や旅行業務のことなどに加えて、異文化理解に関する研修もありました。その異文化理解の講師が開発教育協会の初代代表理事の室靖先生*4であったことを知ったのはずっと後のことでした。
1985年3月25日は、大学の卒業式でしたが、その日は経由地のパリのシャルル・ドゴール空港でパリ出張から帰任するN書記官と、チェコの日本大使館から異動となったN理事官夫妻と合流。パリからの直行便であるUTA*5というエアラインに乗り継ぎ、中央アフリカ共和国の首都バンギの国際空港に降り立っていました。首都の国際空港とは言え、鄙びた地方空港のような風情で、客室内からボーディングブリッジ(搭乗橋)を渡ってターミナルに入るのではなく、機体からタラップ(乗降用の階段)を降りました。すると、そこからターミナルまでライフル銃を肩から提げた兵士が、花道をつくるように両側に等間隔に立ち並んでおり、その間を恐る恐る歩いて行ったことを覚えています。黒光りする本物のライフル銃を間近で見た瞬間、身震いしたことを覚えています。
N書記官の手際の良い入国手続を終えて、空港ロビーの出入口から外へ出ようとすると、外はもう暗く、周囲の照明は裸電球のような明るさでした。行く手を見るとそこにはとにかく大勢の人々がすし詰め状態になって集まっており、気が付くと、自分のスーツケースの取り合いに巻き込まれて、その中のひとりに持ち去られそうになりました。すると、出迎えの大使館の公用車のドライバーが大きな声で叱りつけたかと思うと、すかさず取り戻して公用車のトランクの中に収めました。叱りつけた相手をよく見ると、まだ年端もいかない少年のようでした。その光景に唖然としつつも人混みを掻き分けながら、公用車に乗り込みました。車の中で出迎えに来ていただいた書記官に「あの人たちは何をしに集まっているんですか」と尋ねると、「出迎え、白タク*6や荷物運びの客引き、残りの大勢は見物客ですよ」との答えでした。「スーツケースを持ち去ろうしたのは?」、「チップ目当てに外国人客の荷物を運ぼうと、かれらも必死なんです」。
ここから中央アフリカでの2年間の生活が始まったのです。
*1 アフリカでは定期的に干魃や飢饉に見舞われているが、とくに1984年から85年にかけてエチオピアで発生した飢饉は大規模で、100万人以上が餓死したと言われている。85年7月には英国のロック・ミュージシャンのボブ・ゲルドフの呼びかけで、アフリカ難民救済を目的としたチャリティ・コンサート『ライブ・エイド』が英米をメイン会場として、日本や欧州各地でも同時開催された。2018年の年末から日本でも大ヒットとなった映画『ボヘミアン・ラプソディ』では、英国会場で出演したクイーンの様子が再現されている。なお、これに続く、著名アーティストらによる一連のチャリティ・コンサートに対しては、無関心層の耳目を途上国に向けさせたという評価がある一方で、途上国に対する誤解や固定観念を植え付けたとする批判もある。
*2 「在外公館」とは、世界各国にある日本の大使館や総領事館、国連機関の日本政府代表部などのことで、「派遣員」とは、そこでの後方支援的な業務(とくに便宜供与のほか、庶務や会計などの補佐業務など)に従事する大使館所属の契約職員のこと。外務省から業務委託された一般社団法人国際交流サービス協会が現在でも募集や派遣を担当しているが、現在の業務内容や応募条件は当時とは一部異なっている。
*3 「便宜供与」とは、東京にある外務省本省や他国の日本大使館などからの公用出張者が来訪する際、空港での出入国や通関の業務のほか、滞在中の宿泊・食事や移動・観光の手配などを行う業務のこと。
*4 室靖(むろ・おさむ、1913-1994)先生は、東京高等師範学校を卒業後、東京の公立中学校に美術教師として在職中の1951年に、英国のブリストルでユネスコが主催した国際美術教育セミナーに参加。帰国後の1952年には、創造主義的美術教育の普及推進を目的に、美術評論家の久保貞治郎氏らとともに創造美育連盟を創設するなど、美術教育の改革や国際化に取り組む。その後、ユネスコ技術協力専門家や国際労働機関(ILO)アジア地域担当官として、アフガニスタン(1954~58)をはじめ、イラクやタイなどで活動。1969年から73年まで当時の海外技術協力事業団(現在の国際協力機構〔JICA〕)・青年海外協力隊訓練所長を経て78年まで同顧問を歴任。東和大学国際教育研究所に教授として在職中(1978~1990)に、開発教育協議会(当時)の設立に関わり、初代代表理事(1982-1984)を務めた。
*5 フランス本国とアフリカ、東南アジア、南太平洋などの旧植民地や海外領土とを結んだ当時フランス第二の航空会社。日本にも乗り入れていた時期がある。1990年にエール・フランスに吸収された。
*6 「白タク」とは無許可で営業しているタクシーのこと。日本では自家用車のナンバープレートは白色だが、国土交通省から営業許可を得ると、営業車として緑色のナンバープレートが付けられている。当局から許可を得ずに「白いナンバープレートのまま、違法なタクシー営業を行ってる」という意味で「白タク」という。
2)「大使館」という職場
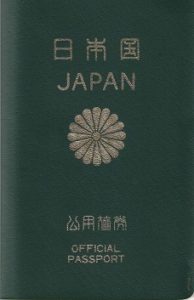
わたしが在勤した大使館の正式名称は、在中央アフリカ共和国日本大使館(L’Ambassade du Japon en République Centrafricaine)といい、同国の首都バンギ(Bangui)の市内に置かれていました。大使館員は臨時代理大使*7(以下「大使」と記す)と書記官と理事官の外交官3名に、その身分をもたない派遣員の私を加えた総勢4名という小所帯でした。これは世界各地にある日本大使館の中でも最小の規模であり、当時は世界で4ヵ国しかなかった瘴癘(しょうれい)度*8が「5」の大使館でした。
日本大使館とは、日本政府の出先機関であり、接受国(外交使節団を受け入れた相手国のこと)に対して政府を代表して主に外交活動や邦人保護活動などを行うところです。具体的には、外交交渉をはじめ、二国間の文化交流や国際協力(ODA)のほか、相手国の政治や経済などさまざまな情報を収集し、自国に報告することを日常業務としています。また、「領事」業務といって、接受国に居住している日本人(在留邦人)の保護や援助、日本企業への支援、テロ対策や在外選挙、出生や死亡、婚姻や離婚などの届出手続、パスポートの更新やビザ(査証)の発給など、多岐にわたる業務を行っています。
バンギの日本大使館では、こうしたさまざまな業務を3名の外交官で分担していたわけですが、逆の言い方をすれば、3名で対処できる程度の業務量だということです。大使館の開館時間、つまり執務時間も平日は午前中のみで、平日の午後と週末は「Fermé (Closed)」でした。これは現地の行政機関の執務時間に合わせての対応なのですが、それにしても仕事が午前中で終わってしまうので、午後の時間をどう過ごすかは、これはこれで結構たいへんでした。これについては、後ほど(6)で少し紹介しましょう。
さて、大使館の職務分掌を簡単に紹介すると、「大使」と書記官は、主に「政務」や「経済」などに関わる外交業務を担当したほか、この書記官は「電信*9」と「領事*10」も担当していました。当時はまだインターネットのない時代だったので、日本の外務省(「本省」という)やパリの日本大使館などとの連絡は専用の通信回線で繋がれた通信端末(たしか“テレックス”)を使っていたと記憶していますが、その業務のことを当時は「電信」と言っていました。外交に関わる機密情報などを送受信するので、その通信内容は暗号化する必要があり、その暗号コードは大使館の中でも専用の電信室で厳重に管理されていました。派遣員であるわたしは電信業務には一切携わらず、電信室には一度も入室したことがありませんでした。
中央アフリカには当時、10名程度しか在留邦人がいませんでした。その10名とはわたしを含めた大使館員4名とその家族のほかは、政府開発援助(ODA)の関係で当時の国際協力事業団(JICA)から長期派遣されていた専門家や、無償資金協力事業の一環で地下水開発事業(要するに「井戸掘り」)のために長期滞在していた民間企業の技術者など数名でした。大使館に来訪する日本人と言えば、日本からの観光客はほとんど皆無でしたが、たまに隣国のカメルーンやガボンに駐在していた日本の総合商社の駐在員が訪ねてくることがありました。その程度だったので、邦人保護などの「領事」に関する業務はほとんどありませんでした。査証の発給も、たまに技術研修か何かで日本に派遣される政府関係者ぐらいのものでした。もうひとりの館員である理事官は会計・文書・庶務といった業務を担当しており、その理事官の下で私は補佐的な仕事をしていました。
ほかにも当時の天皇誕生日(4月29日)には、大使公邸で祝賀レセプションが開催され、「大使」以下、館員総出でその準備にあたりました。とくに最初のレセプションは、着任してまだ1ヶ月のことだったので、事情も勝手もわからず、ただ右往左往していたことを思い出します。
*7 臨時代理大使とは、外交使節団の正式な長である特命全権大使ではなく、一般的には、大使の一時的な海外出張や病気療養などの際に、次席の大使館員(公使や一等書記官など)が、文字通り、臨時で大使の職務を代理する職位のこと。「臨代(りんだい)」と略称される。ただし、諸事情によって相手国から日本に特命全権大使が派遣されていない場合は、外交上の相互主義の観点から日本からも相手国に特命全権大使を派遣しない場合がある。中央アフリカの場合、1968年に駐日大使館を開館した当初は特命全権大使が赴任していたものの、その後の政情不安や財政事情などから大使が派遣されていなかった。なお、駐日大使館は1992年に閉館。バンギの日本大使館も2005年に閉館し、それ以降は在カメルーン日本大使館が中央アフリカを兼轄している。
*8 「瘴癘(しょうれい)度」というのは、生活困難の程度のことで、外務省では在外公館が置かれている国の気候や風土をはじめ、治安状況や衛生状況など、赴任地での社会環境や生活環境の考慮して、当時は各公館を5段階に区分しており、もっとも環境が厳しいのが「5」であった。その区分に応じて海外勤務に関わる手当の金額が変わり、健康診断や治療・療養などを目的とした「健康管理休暇」という長期休暇を赴任中に取得することができた。なお、当時「瘴癘度5」の国は、中央アフリカを含めて、アフガニスタン、ギニア、ハイチの計4ヵ国であった。
*9 当時の外務省大臣官房には「電信課」があり、電信の取扱いが多く、館員も多い在外公館では、電信専従の「電信官」という職位も存在した。インターネットが普及してからは課名は「情報通信課」と改称されている。
*10 在外公館の中でも、国土が広く、在留邦人の多い米国や中国のような国々では「領事」業務だけを行う総領事館や領事事務所が置かれている。
3)わたしの担当業務

わたしが担当した業務は、文書と庶務の仕事でした。大使館と本省との間では、業務上の情報や資料がやりとりされています。その情報の中でも緊急性が高いものは上述の「電信」で送受され、「公電」と呼ばれます。緊急性が高くないものは文書の形で航空便等で送受され、こちらは「公信」と呼ばれます。前者の公電を担当するのが「電信(班・係)」で、後者の公信を担当するのが「文書(班・係)」です。
文書という仕事は、大使館から本省に発出する公信に文書番号を付し、大使館の公印を捺印するなどして書類としての書式を整えたり、逆に本省から送付されてきた書類や資料を館内で回覧した後、保管管理する業務です。外交文書を送受する際には「(外交)パウチ*11」という巾着式の専用袋を使うのですが、小さな大使館だったので、パウチに封入する書類などの量は少なく、紐で縛って赤い封蝋で封印する小さな厚手の布袋を1袋か多くても2袋で間に合っていました。他方、中央アフリカは郵便事情が劣悪だったので、大使館員の家族宛(その逆もあり)の手紙もこのパウチの中に入れることが認められていました。バンギ-パリ間の直行便が週1便だけだったので、その日に空港まで持参して通関手続を済ませ、日本から届いたパウチを引き取ってくるのが仕事でした。たまにそのパウチが届いていないと空港の係官からむげに言われたことがあるのですが、航空便で送付済みのパウチが届いていないとなるとこれは外交機密上の一大事です。しかし、必ず空港のどこかに留め置かれているので、それを探し出すのも私の仕事だったわけです。
「庶務」というのは、そのほかの種々雑多な仕事で、館内で必要な備品や日用品などの物品を市内で調達したり、大使館の建物、といっても民間の平屋の家屋を借り上げたものですが、壁にヒビが入ったとか、配線が切れたとか、雨漏りがするとか、そういったトラブルに事欠くことがなく、まず対処するのがわたしの仕事でした。また、上司であった理事官が、語学が不得手な方だったので、ローカルスタッフに指示を伝えるのも私の役目でした。大使館のローカルスタッフとしては、大使の専用車と館員用の公用車の運転手がそれぞれ1名、警備を担当する警備員1名、大使館の敷地内の樹木などを管理する庭師1名、そして、かれらの取りまとめ役のようなセクレタリーが1名の合わせて5名と、そして大使専属のフランス人のセクレタリーも1名いました。まとめ役のセクレタリーは名前をトーマ(Thomas)さんといい、中央アフリカでは数少ない高卒資格を持ち、英語を話す唯一のローカルスタッフでした。私のフランス語も怪しかったので、ほかのスタッフに何か依頼するときは、彼に英語からフランス語への通訳を頼んでいました。つまり、指示系統は、理事官→派遣員(私)→トーマさん→ローカルスタッフという伝言ゲームとなっていました。
派遣員が担当する本来業務は便宜供与なのですが、中央アフリカへの公務による出張者は在任中の年間で数件程度だったので、便宜供与の業務自体はほとんどありませんでした。任期中に、大使館に来訪した一般の日本人も上述の通りきわめて少なく、現在でも記憶に残っているのは3名だけです。そのうちのひとりはアフリカをリヤカーで横断(か縦断)していた私と同年代の若者でした。2人目は、アフリカで植林活動を始めたいということで、そのプロジェクト地の事前調査に訪れた人でした。お名前は高◯◯馬さんといいますが、後に「サヘルの会*12」というNGOを日本で立ち上げ、中央アフリカではなく、西アフリカのマリでプロジェクトを始めた方です。高◯さんとは、私が日本に帰国した後、NGO活動推進センターの仕事をする中で再会しました。最後のもう1人については、後述することにします。
*11 正式には外交行嚢(がいこうこうのう)といい、英語では diplomatic pouch や diplomatic courier という。この外交行嚢には外交特権が適用され、相手国は税関等で開封して中身を検査することができないこととなっている。
*12 高○氏がアフリカのサヘル地域での調査を終えた1987年に設立。その後、1991年に「緑のサヘル」を新たに設立。なお、サヘルの会は設立10年後の1997年に団体名を「サヘルの森」に改称している。
4)中央アフリカという国家
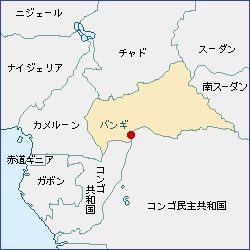
わたしが2年間を過ごした中央アフリカという国ですが、アフリカの地図を見ると、アフリカ大陸のほぼ真ん中に位置しています。このことは地政学的に重要な地域であることを意味しており、19世紀末から1960年の独立までの間はフランスがこの地域の実権を握っていました。独立以降もフランス政府はフランス軍を駐留させたり、中央アフリカ政府の要所には、フランス政府の関係者が顧問という肩書きで配置され、政治的軍事的な影響力を維持していました。また、中央アフリカをはじめ、隣国のチャドやカメルーンなど中部アフリカ6ヵ国はCFA(セーファー)フランという共通の通貨を使用していましたが、為替は当時の1フランス・フラン=50CFA(=日本円で約25円)と固定され、フランスフラン以外の外国通貨とは両替ができませんでした*13。つまり、通貨を固定相場とすることで、経済や金融の面でもフランスは旧植民地諸国を管理していたのです。しかし、1960年の「アフリカの年」に独立した中央アフリカもそれ以来、クーデターや武力対立が絶えることはなく、旧宗主国のフランスですら事態を収拾できなくなるほど、深刻な混乱や凄惨な悲劇を招くことになりました。
たとえば、2012年末から、イスラム系反政府民兵組織のセレカ(Séléka)とキリスト教系反政府民兵組織のアンチバラカ(Anti-Balaka)、そして中央アフリカ政府との間で三つ巴の内戦状態に突入。これに国連のPKO部隊やアフリカ連合(AU)の多国籍軍が派遣されたものの、両民兵組織による一般市民に対する虐殺や略奪、放火や性暴力が横行するなど、実に凄惨な事態に陥りました。その結果、人口数百万の国で100万人以上が難民や避難民となっていると報告され、「世界でもっとも無視された避難民危機*14」と指摘されています。現在でも政情不安や武力対立が常態化しており、日本の外務省の危険情報では中央アフリカ全土で「退避勧告(レベル4)」が継続中です。しかし、日本のメディアもこの国の実情をほとんどまったく報道してこなかったため、日本でこの国をよく知る人はきわめて少ないでしょう。こうした中央アフリカの現状はいわば「崩壊国家」であり、無政府状態とも言えます。直近の状況について関心のある人は、国際NGOの国境なき医師団(MSF)や国連UNHCR協会のほか、AFPBBニュースなどの関連サイトを視聴してみて下さい。
他方、中央アフリカは、ドルーリーオオアゲハというアフリカ大陸最大の蝶が生息するなど、蝶類の種類の豊富さでは専門家や収集家の間で世界的に知られています。また、隣国のカメルーンとコンゴ共和国との国境地帯には「サンガ川流域の3か国保護地域」という世界自然遺産があり、貴重な生態系やマルミゾウなどの絶滅危惧種が保護されています。しかし、長引く紛争が武装集団による象牙の密漁を許しています。そのほかにもダイヤモンドなどの鉱産資源にも恵まれてはいますが、そのダイヤモンドも今では武装勢力の資金源となり、いわゆる「紛争ダイヤモンド(Conflict Diamond)*15」として、取引が制限されています。
勤勉で朴訥とした中央アフリカの人々に、平穏な日常が一日でも早く戻ることを願わずにはいられません。

*13 CFAという通貨は、フランスが西アフリカを含めた植民地時代から使用してきた共通通貨で、もともとは「フランス領アフリカ(Colonies françaises d’Afrique)」という意味。各国の独立後は「アフリカ金融共同体(Communauté financière africaine)」などのように読み替えられている。また、ニジェールやコートジボワールなどの西アフリカ8ヵ国では発券銀行の異なる別のCFAフランが流通している。いずれも1994年には1フランスフラン=100CFAに切り下げられ、1999年のユーロ(EURO)導入後は、1ユーロ=約656CFAに固定されている。なお、最近の報道によれば、西アフリカ諸国が連合して統一通貨「ECO」の導入が議論されているという。
*14 NGOのノルウェー難民評議会(NRC: Norwegian Refugee Council)では、①事態の収束に向けた当事者間の政治的意思の欠如、②報道機関の関心の欠如、そして③経済的支援の欠如の3つの基準から、毎年『世界でもっとも無視された避難民危機(The World’s Most Neglected Displacement Crises)』報告書を公表。その2017年版で中央アフリカはワースト1位となっている。
出典:NRC, “The World’s Most Neglected Displacement Crises,” (Jun 2017).
*15 紛争ダイヤモンドについては、たとえば、NPO法人ダイヤモンド・フォー・ピースのウェブサイトを参照。また、西アフリカのシエラレオネを舞台に紛争ダイヤモンドの実態を描いた映画『ブラッドダイヤモンド』(主演:レオナルド・デュカプリオ)が2006年に公開されている。
5)ある日の出来事
ある日のことですが、書記官から一緒に来て欲しいということでバンギ市内にある唯一の国立病院に公用車で向かいました。この病院にはかつて書記官と視察で訪れたことがあるのですが、国立病院とは言っても、建物や設備は老朽化しており、病室は患者や付き添いの家族であふれ、廊下では煮炊きをしている状況でした。なぜ病院の廊下で煮炊きをしているのかというと、運良く入院できた患者の中には地方から何日もかけて命からがらたどり着いた人も少なくなく、付き添いの家族も帰るに帰れず、病院内に寝泊まりするようになるのです。病院とは言え、衛生状態は悪く、冷房もなく湿度も高い空気に、消毒液をはじめ、汚れたリネンや半乾きの洗濯物、そして料理や食材などの臭いが混じり合ったその光景にはただ唖然とするばかりでした。
この日は病院の担当者の案内で、病院の片隅にある霊安室を訪れたのです。そこにはご遺体が安置されていたのですが、病院の担当者が「日本人です」と言うのです。記憶の範囲で思い出すと、この日本人は市内のホテルで滞在中に亡くなり、ホテルから病院に搬送され、死亡が確認されたのです。身寄りがないため大使館に連絡が入ったということですが、この日本人は70歳を越えた年配の方で、実は、この方とは市内のレストランで偶然出会って食事を一緒にしたことのある人でした。その後も車で移動中に市内を歩いているところを見かけることもありました。
このような事態になると、大使館はどうするか。まずご遺体の身元をパスポートなどで確認し、東京の本省を通じて日本にいるご遺族に連絡を取ります。そして、ご遺体をどうするのか、ご遺族の意向を確認するのですが、選択肢は2つです。ひとつは現地で荼毘(だび)に付して、遺骨を日本に搬送する。もうひとつはご遺体そのものを日本に搬送するです。この時にご遺族が選択したのは後者でした。バンギの日本大使館にとっては在留邦人の死亡という案件は初めてのことで、館員全員が対応に追われました。
領事担当の書記官と市内中心部の滞在先のホテルに向かうと、そこは私が赴任当初、まだ住居となる外国人向けのアパートが見つからないときに、3ヶ月ほど滞在していたホテル・ミネルバという中級レベルのビジネスホテルでした。ホテルの従業員とも顔見知りでしたが、その一室に入って、遺品を確認し整理しました。以前、一緒に食事をした時に、滞在目的を尋ねたのですが、たしか「ビジネスで・・・」という返事だったと記憶しています。中央アフリカで日本人がビジネスというのも腑に落ちませんでしたが、何のビジネスなのかは深く尋ねませんでした。しかし、遺品を整理していると、同じ名前で異なる会社名や肩書きの名刺が何種類も見つかり、どうやらダイヤモンド関係のビジネスで滞在していたことがわかりました。中央アフリカのダイヤモンドは宝石になるような高品質のものは少なく、大半は工業用のダイヤモンドなのですが、かつては日本の企業も参入していたそうです。しかし、その後採算が合わなくなり、日本企業は撤退し、当時は韓国系の企業が採掘や流通に関わっていたようです。
さて、ご遺族の意向に応えるために、遺体搬送の準備をしたのですが、これがまた大変でした。ご遺体を空輸するにも、パリ行きフライトは直行便が週1便、隣国チャドの首都ンジャメナ経由のエール・アフリク(Air Afrique)も週1便だったので、次の便までたしか3日ほどあったのです。しかし、病院の霊安室にあったエアコンは故障して動かず、ここにこのままご遺体を安置していれば、腐敗が進んでしまいます。そこでどうしたか?書記官や理事官と考えあぐねた結果、「氷で冷やすしかないだろう」ということになりました。そのためには大量の氷が必要でしたが、市内のスーパーなどでは「氷」は売っていませんし、この国で「氷」は貴重品です。どこに行けば大量の氷が入手できるか見当が付きませんでした。すると大使専属のフランス人秘書が「ビール工場*16で手に入るのではないか」と機転を利かせてくれました。早速、ビール工場に連絡を取って事情を説明してもらうと、取りに行けば必要なだけもらえることになりました。
そこでわたしが氷の調達・運搬係に任命されてビール工場に急行しました。しかし、そこで出てきた「氷」とは、大型の製氷機からそのまま出てきた線路の枕木のように太くて長い氷柱で、想像していたモノとはまったく違っていました。工場の担当者に「何本必要なんだ」とか「トラックはあるか」とか言われたのですが、大使館の公用車は日産のセドリックで氷を運ぶための車ではありません。今からトラックを手配していては間に合わないので、公用車のトランクに入るだけ入れて病院に運びました。ただ1回で運べる量は限られているので、何度か往復したように記憶しています。霊安室では病院のスタッフの助けを借りて、枕木のような氷を何本か並べた上にご遺体を置き、砕いた氷を入れたビニール袋をその周囲に置くなどしました。そこまでしても、氷は溶けていってしまうので、たしか朝昼夕と、ビール工場と病院との間を往復し、同じ作業を3日間ほど繰り返しました。他方、大使館ではご遺体を日本に空輸するための諸手続のほか、日本までの空輸に耐えうる棺を市内の木工業者に特注するなどして搬送の準備を進めました。
パリまでのフライトがあった日、棺を誰がどうやって空港まで搬送したのか記憶にないのですが、ご遺体は無事にバンギの地を離陸し、こうして日本人の遺体搬送という一生忘れることのできない任務は完了したのです。後日、外務省経由でご遺族からお礼の連絡(手紙?)が大使館に届いたことをかすかに記憶しています。

*16 中央アフリカにはMOCAFという飲料会社があり、モカフ(MOCAF)やカステルビール(Castel Beer)という商品名のビールを製造販売していた。
6)バンギでの日々の生活
バンギでの日々の生活は、毎日が混乱と困惑の連続でした。停電や断水は日常茶飯事であり、電話や郵便もほとんど機能していませんでした。外国人用のアパートに住んでいたとは言え、乾期ともなれば、蛇口から水が出てくる時間はとても限られていたので、蛇口は常に全開にしてバケツに水が貯まるようにしていました。貯まったとしても水は濁っているので、洗髪するときなどは、スーパーで買ってきたミネラルウォーターで流していました。困ったのはトイレです。水洗式であることがかえって問題で、水が流れるはずがありません。それで貯めた水で流していたわけです。
郵便も市内の郵便局からは出さないようにと大使館から注意されていました。その理由はエアメール(航空便)に貼ってある切手の料金が高く、郵便局員の中にはその切手をはがして転売する不届き者がいるのだとか・・・。そのため郵便を出すなら、管理が厳しい空港内の郵便局から出すようにとのことでした。電話をするにも今のように携帯電話がなかった時代であり、かと言って公衆電話があるわけでもないので、日本の家族に電話するのは盆と正月くらいなものでした。市内にある電話局に出向いて、窓口で日本への国際電話であることを伝えてから、専用の個室に入って受話器を取るという旧式でした。こんな電話のかけ方も生まれて初めてでしたが、いくらも話していないのに、結構な金額を請求されたと記憶しています。
盗難の被害にも遭いました。バンギでの通勤や移動には、前任の書記官から買い取ったトヨタ・カローラ*17に乗っていました。アパートの1階に住んでいたので、部屋の前の空いたスペースに駐車していました。ある日、出勤しようとして玄関ドアを開けた瞬間、呆然としました。タイヤが4本ないのです。マンガの1コマのようですが、犯人側は車のフレームの下にブロックを挟み込み、車体を浮かせてタイヤを外していったのです。またある日、クルマのエンジンをかけようとすると、かかかりません。ボンネットを開けると、今度はバッテリーが跡形もありません。こうしたタイヤやバッテリーの盗難は珍しくないことを後で知ったのですが、以来、クルマはアパートの裏手に駐車することになりました。そのアパートには「ガルディアン(Gardien)」と呼ばれる警備員がいたのですが、彼はなんと24時間(!)勤務、つまり“住み込み”だったので、深夜は裏手にある休憩所で休むのです。さすがに夜くらいは寝ないともたないので、物音がすれば気が付くように、彼の寝床の近くに駐車しておくようにしたのです。
それから、いよいよ日本に帰国する直前にも盗難に遭いました。大使館から戻ると、玄関のチェーンが切られ、アパートの部屋の中が物色されていました。すなわち、白昼堂々の犯行ですが、警備員を問いただしても「知らない」の一点張りでした。とはいえ日本で必要なものは別便ですでに送付した後だったので、ほとんど影響はなかったのですが、現地職員から譲って欲しいと頼まれて残しておいた自転車やラジカセ、食器類などは持ち去られていました。バンギでは赴任していた外国人が帰国間際に盗難に遭うケースが多いのです。帰国間近なので警察に被害を届けることがないからだそうです。なので、いつ帰国するかは関係者以外には秘密にしておくのですが、やはりどこかから情報が漏れてしまうようです。
このように、日本とは勝手が大きく異なる場面や日本ではなかなか経験できないような“事件”に遭遇しつつも、何ヶ月か経つと、大抵のことには動じなくなっていました。その一方で、先に大使館の仕事が午前中だけであることを紹介しましたが、娯楽の少ないバンギで、平日の午後や週末をいかに過ごすかは、健康管理上、そして精神衛生的にもとても重要でした。
そこで時間を費やしたのがゴルフでした。バンギの郊外に、フランス人がオーナーを務めるゴルフクラブがあって、ほぼ毎日と言ってよいほど通っていました。ゴルフクラブと言っても設備は簡素で、コースは18ホール(確かパー70?)までありましたが、日本のテレビで見るゴルフ場とは雲泥の差で、フェアウェイとラフの区別がつかない原っぱのようなコースでした。グリーンも芝生ではなく、サンドグリーンと言われるもので、グリーン全体が砂場になっていて、真ん中にカップが切られているだけのものでした。砂地なので、人が歩くと足跡が付くため、いわゆる“トンボ”を使って、ボールとカップの間の砂の表面を均してから、パットをするのです。私自身、ゴルフは初めてでしたが、私の赴任の直後に帰任した書記官からゴルフセットを譲り受けていました。ほかの館員に連れられて行った最初の日に、ゴルフクラブの会員となり、登録料を払いましたが、それほど高い金額ではなかったと記憶しています。最初は打ちっ放しのスペースで見よう見まねで練習していましたが、ほかの館員がコースに出るというので、いきなりコースに出て行ったのです。慣れてくると自分1人で出かけて行くこともありましたが、午後の炎天下の中で、何キロか歩くわけで、かなりの運動量にはなりました。ラウンド後にはクラブハウスで冷えたビールを飲むのが何よりの楽しみでしたが、おそらくこのクラブハウスのビールがバンギでいちばん冷えたビールだったと記憶しています。ちなみに、ゴルフはまったくの素人であった私ですが、日本に帰国する前には、ハンデ10を切るくらいの腕前にはなっていました。たしかこのコースは18ホールでパー70だったので、調子がよければ80を切っていたということです。ただし、帰国後から現在に至るまで、日本でゴルフをする機会はまったくありませんでした。
そのほか、外国人専用のテニスクラブに入会できることが分かって、テニス好きのK書記官とときどき出かけていきました。書記官と理事官の住居である館員宿舎には久しく使用されていなかった小さなプールがあったのですが、それを改修しようということになり、改修後に水浴びに行ったりしていました。また、週末の夜には大使公邸や館員宿舎での夕食に招かれることも多く、食事の後は夜遅く(時には朝方)まで雀卓を囲むのが常でした。
それから今でも記憶から離れない出来事は、マラリアにかかったことです。赴任当初は感染予防のためにニバキン(Nivaquine)というマラリアの予防薬を服用していたのですが、何週間もすると服用を止めていました。ある日、目が覚めると、ベッドから起き上がれないのです。激しい悪寒がして、手足に力が入らず、声を出せないのです。金縛りにあったような状態となり、このまま死んでしまうのではないかと、本気で焦りました。幸い、平日だったので、時間になっても出勤してこない私を心配して、N理事官が様子を見に来てくれました。アパートの中にどうやって入れたのかは分かりませんが、多分、アパートの大家さんから合鍵を借りたのでしょう。私の様子が変だということで、抱きかかえられながらなんとかN理事官のクルマに乗ると、韓国大使館に在勤する医務官の先生のところへ連れて行ってもらいました。
医療事情が厳しい、いわゆる“途上国”では、外国人専用の病院やクリニックが運営されている場合が多いのですが、ここ中央アフリカにはそうした医療施設はありませんでした。そのため各国大使館は館員や自国民に医療を提供するために医務官を置いたり、自国民専用のクリニックなどと提携しています。日本政府も館員の多い大使館や地域の拠点となる大使館には医務官という医師が配属されているのですが、中部アフリカ地域では、当時のザイール(現在のコンゴ民主共和国)の日本大使館に医務官が配属されているのみで、たしか年1回、周辺国の大使館員やその家族の健康診断や保健相談のため巡回していたように記憶しています。
さて、その韓国大使館の医務官の先生は、シン(申?)先生といいましたが、日本語を話す親日家で、こちらの事情を察して何かあれば連絡してほしいと日頃から声をかけてくれていました*18。診察の結果、40度を越える熱がありました。脱水症状にならないように水分を取って安静にしているようにということで、その日は、抗マラリア薬を処方してもらいました。しかし、翌日になっても熱は下がらず、手足の指先の感覚もなくなっていました。高熱が続くのは危険だということで、今度は特効薬のキニーネを注射してもらいました。キニーネという劇薬は、現在ではほとんど処方されないようですが、マラリアが抗マラリア薬に対する耐性を持っている場合は、当時はまだ処方されることがあったようです。そのキニーネのおかげで熱は下がり、一命を取り留めることができました。
盗難はともかく、このマラリアにかかったという出来事は、私にとっては“大事件”でした。マラリヤは対応を誤れば、命を落とすかも知れない怖い熱帯病で、その時はなかばパニック状態に陥りました。しかし、この体験が、その後の私の進路に少なからずの影響を及ぼすことになったのです。(Mar. 10, 2021; rev. Apr. 12, 2021)
*17 当時のカローラ1台の価格は日本で100万円を切っていたが、現地バンギにあったトヨタのディーラーでの販売価格は日本円で300万円程度だったと記憶している(が、この金額は免税価格だったかも知れない)。このことからも分かるように、アフリカの内陸国である中央アフリカでは、海外からの輸入品や海外への輸出品に多額の輸送コストがかかり、経済活動への負担となっている。
*18 娯楽の少ないバンギでは、韓国大使館のシン先生とは上述のゴルフクラブでよくお会いした。ラウンド後にゲストハウスでビールを一緒に飲んだりする機会がたびたびあった。
7)中央アフリカが教えてくれたもの
日々の生活や仕事の中で目を丸くしたり、開いた口が塞がらないような状況に遭遇しつつも、私は中央アフリカから多くを学びました。と言うよりも、中央アフリカが私にいろいろ教えてくれたと言った方がよいでしょう。それを一言で言えば「“南”の世界の一端に私が出会う機会を与えてくれた」ということです。このことが帰国後にNGOの仕事に私を向かわせる原体験となり、原動力になったのです。
その「原体験」とは、「貧困」という問題の深刻さや複雑さを目の当たりにしたということです。世界第2位の経済大国と言われた日本の中で育ち、苦労らしい苦労もせず、何の不自由も感じることなく生きてきた私にとって、「貧困」という問題が意味することなどまったく分かりませんでした。しかし、わずか2年間という短い期間ではありましたが、日々の仕事や生活の限られた場面から、この国の置かれた状況、そして“途上国”と呼ばれる多くの国々にも共通した「貧困」問題の重大さを肌で感じることができたのです。
たとえば、次のような場面が今でも蘇ってきます。大使館では何名かの現地職員を雇用していることを紹介しました。当然、かれらには毎月、給与の支払日があり、現金で支給していました。私が着任して最初の支払日のことです。私と一緒に着任した会計担当のN理事官から給与は手渡されるのですが、受け取る順番が決まっていたようで、支払額の多い順に職員が部屋に入ってきて、金額を確認すると受取のサインをしていきます。最初は、大使付きのフランス人セクレタリー、そして現地職員のまとめ役のセクレタリーのトーマさんと続きます。この二人はもちろん自分の氏名をサインしていきました。3人目は確か大使専用車か公用車の専属ドライバーだっと思いますが、受取のサインをしてもらおうとすると、そのサインが丸く塗りつぶしたような小さな黒い点だったのです。私とN理事官は思わず顔を見合わせました。これがサインかどうか何度も確認したのですが、自分のサインだと言うのです。まとめ役のトーマさんに間に入ってもらっても、やはりそうだと言います。次の職員のサインはギザギザの波線のようなサインでした。こうしたサインを書くのがこちらの習慣なのかも知れないと思いましたが、後でトーマさんに確認してみると、かれらは文字が書けないので、あのようなマーク(しるし)を書いているとのことでした。この場面は私にとって衝撃的でした。文字の読み書きができないということを初めて知った瞬間でした。
もうひとつの場面を紹介しましょう。週末に食事に呼ばれて公邸や館舎で夜更かしをしていたことを紹介しましたが、深夜になって自宅のアパートに車で帰る途中に大通りを走っている時に、その街灯の下で何かを読んでいる人たちをよく見かけました。特に乾期になると停電が多く、夜は街の中が真っ暗になることもあるのですが、空港や大統領府などに通じる大通りだけは煌々と灯りが点いていることがあるのです。そうした人たちを何度も見かけていたので、ある日、車の速度を落として近くを走ってみると、その人たちはまだ若く、読んでいるものも雑誌や新聞などではなく、背表紙の厚い本を読んでいました。おそらく、バンギでは数少ない大学生か高校生だったのかも知れません。「蛍雪の功」という言葉は日本ではもはや死語ですが、若者が限られた灯りを頼りに勉学に勤しんでいた姿は今でも記憶から離れていきません。
このように、日々の仕事や生活を通じて、見ることや聞くことのすべてが私の中に染みこんでくる中で、私は「豊かさ」と「貧しさ」との間の葛藤や相克に動揺し、「開発」や「近代化」の虚構や矛盾について考えざるを得ないような心境に追い込まれたのです。
もうひとつの「原動力」とは、「知ったことを伝えなければならない」という衝動に駆られるようになったということです。中央アフリカをはじめ、“途上国”と呼ばれる国々や地域に暮らす人々が貧困から抜け出すことの出来ない状態にあることを知らされた私は、“途上国”だけでなく、あのアメリカでさえ国内に貧困問題を抱えていたことを思い出しました。世界には不条理や不公正というものが存在する。日本にいた時には気づきもしなかったこのことに、私は改めて愕然としたのです。そうした腑に落ちないモヤモヤとした気持ちのはけ口を失って、「こんな重大な問題を今まで誰も教えてくれなかった」と私は八つ当たりをするようになったのです。それをきっかけに、日本の学校や大学の中では“途上国”の問題はどのように扱われているのだろうか、そして、日本のメディアはアフリカの問題をどのように伝えているのだろうか、と私の関心は、日本の教育やメディアのあり方にも向かっていきました。
日本の教育もメディアもアフリカの現実や真実を伝えていないのであれば、それなら、知ってしまった自分が伝えるしかない、それが知ってしまった者の責任ではないかと、何やら悲壮な正義感や稚拙な使命感に縛られてしまう時期もありました。いずれにしろ、「自分が知ったことは伝えていかなくては」という気持ちだけは、日本に帰国するまで消えることはありませんでした。
8)〔番外編〕『夢枕〔バンギ編〕』
➡ 閲覧希望の方は「パンドラの箱」へ(準備中)
地球のことば(7)


問題は過去を克服することではありません。さようなことができるわけはありません。
後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはまいりません。
しかし過去に目を閉ざす者は結局のところ現在にも目を閉ざすことになります。
非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすいのです。
・・・
若い人たちにお願いしたい。
・・・
若い人たちは、たがいに敵対するのではなく、たがいに手をとり合って生きていくことを学んでいただきたい。
リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー(Richard von Weizsacker 統一ドイツ初代大統領 1920-2015)
出典:リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー『荒れ野の40年:ヴァイツゼッカー大統領演説(全文)』永井清彦(訳)、岩波ブックレットNo.55、岩波書店、1986年、16, 36頁。ただし、出典にある「盲目となります」を「目を閉ざすことなります」と改訳した。なお、現在では同ブックレットの新版(2009年)が入手可能。